|
□ 雪風 □
白く染まり行く空に、歓声が上がる。 息が真っ白に染まる…そんな寒い朝の散歩途中、薄靄の中に朧に見える家。 ここまで来たのは初めての事だったから、今まで気づきもしなかった。 “こんなところに…” すぐそばまで来ると、南に面した扉の上に大きなベルが見え、朽ち果てていない様子から、ここに未だ誰かすんでいるのは一目で分かるが、周囲に他の家の形はない。 町から離れたこんな寂しい場所で暮らす住人とは、一体どんな人物なのだろう。 少しの興味を覚えたものの、好奇心から扉を叩くような真似は出来ずに、私はその場から離れようと踵を返した。 ところが― 「うわっ…」 急に強い風が吹いて、よろけた私は身体を壁にしたたか打ちつけた。 立ち上がろうとしたところに、カラコロとベルの音。風のいたずらにしては大きくて、振り返る間もなく、声がかけられた。 「どなたですか?」 開いた扉から顔を出していたのは、まだ年若く見える女性。慌てて立ち上がった私は、非礼を詫びた。 「すみません。散歩途中だったのですが、風に煽られてしまいまして」 頭を下げる私にくすりと笑った女性は、少しの間を置いて言った。 「この風では戻るのも大変ですね。少し止むまで、休んで行かれませんか」 寒さでツルツルと滑る地面を踏みしめ、風に気を付けながら帰る困難さを頭に思い浮かべた私は、その言葉にありがたくお邪魔させていただく事にした。 「お客さん?」 小さくか細い声が部屋の隅から聞こえ、視線をそちらに向けると、寝台の上に横たわる少女の姿があった。女性はこの子の母親なのだろう。うっすらと笑みを浮かべて少女の髪をなでた。 「えぇ、風で迷い込まれたのよ」 会釈した私に、少女は本当にかすかな微笑みを向けると、窓の外をぼんやり眺め始めた。 差し込む光に透けてしまいそうな姿に“前にもこんな事があったような”と記憶に引っかかるものを覚えて、目が離せない。 しばらく見ていると、かちゃりと音がして、白い物で視界がわずかに揺らいで見えた。思わず目で辿った私の前には、温かな湯気を立てる薄桃色のティーカップ。差し出してくれた女性は、椅子に座るよう私に促すと、そんな少女を悲しげに見て言った。 「あの子は、不治の病に冒されているのです。最後になるかもしれない願いを聞いてあげたいけれど…」 その言葉によく見れば、寝台のすぐ横にはこの世界に来て知った機械の一種と思われる物が置いてある。 人工生命維持装置―今までは話に聞くだけだったけれど、これが少女の命を辛うじてこの世に繋いでいるのだろう。こぽこぽと音を立てる機械から、細い管が少女へと伸びていた。 “そうだ。似ているんだ…出会った頃のあの方に“ 今では、とてつもなく元気なあの方ではあるけれど、出会った時には、何かあるとすぐ倒れる程にか弱い子供だった。 『あんなに小さくてさ、あんなに可愛いのに、今のままじゃ長くないんだぜ』 言い出せない思いを口にするよう、密やかに…けれど、重々しい溜息とともに吐き出された言葉。 そんな死の宣告すら受けているほどに― 昔聞いた物がよみがえって、横たわる少女に幼いあの方の姿がかぶって見えた。 窓の外を見ながら、彼女は小さな声でポツリポツリと口にする―きっと母親には聞こえていない呟き。 「私、もうすぐ消えちゃうのかな…」 「クリスマスまで生きたいな…」 “あぁ、この少女は知っているんだ…” 自分の命がそう長くはない事。受け止めた上での小さな望み。 あの方には未来へと繋がる希望があった。けれど、目の前の少女には…それなら、せめてその願いだけでも叶えてあげたい。 「今年は雪が降るのかな…」 最後の呟きに、私は考えをめぐらせた。 今日はこんなに寒いのだから、雨雲さえ呼び寄せたら雪が降るだろうが、そう出来るだけの力が今はない。これが、自分の世界なら容易い事なのに。 「せめて人工的に作ってでも見せてあげたいわ…」 半ば諦めを含んだ母親の言葉に、はっと顔を上げた。 『向こうの世界では人工的に雪を降らせることだって出来たんだよ』 ―そう言っていた事を思い出す。命を繋ぐ物があるのなら、雪を降らせる物もあってもおかしくは無いはず。 その機械の事を母親に尋ねると、あるけれど高価なものだと言う。 でも、存在しているのなら… 風が優しくなったのを見計らって、私は心当たりを尋ねた。 「廃棄処分?」 「えぇ、前作のは欠陥だらけだったので、新型のは開発ちゅ―」 相当、凶悪な表情だったらしく、カウンターの向こうに座る彼は顔を引きつらせて言葉を途切れさせた。 “欠陥だらけだったのでは、仕方ないじゃないですか” これ以上彼に聞いても埒があかないと判断して、他の方法がないかと、説明しながら人を訪ね歩くと、何人目かでようやく色よい返事が返ってきた。 「そういうことなら協力させてもらうわよ。ねぇ、あれ廃棄した場所ってどこだったかしら?」 快諾してくれた女性は、後ろで作業をしている人たちに声をかけた。 どこだったかとその場がざわめく中、一人の男が大声で返してきた。 「あんなばかでかいブツを捨てれる場所は、あそこぐらいのもんだろうよっ!」 彼の言ったのは、私も見た事がある場所だった。 雑多に物が積まれていて、一体何があるのかと思った事もあったけれど、確かにあそこなら捨てられていそうなものだ。 「とにかく見つけ出してきて。持ってきたら使いものになるように出来ると思うから」 頷いた私は、指示された場所へと向かい、相変わらずうずたかく積まれた物から、目当てのものを探した。 「あった!」 何とか抱えられるかどうかぐらいの大きさの物が、ゴミの山から姿を現した。ところどころ、壊れているようにも見えるけれど、製作に携わった人になら何とかなるかもしれない。何せ無からこれを作り出したわけなのだから。 重いそれを抱えていくと、彼女は仔細に調べていった。 「大丈夫!直せないほどじゃないわ」 彼女の指示するままに、機械に慣れない手を加えていき、そうして直った物を持って― カランコロンとベルが鳴る。 少女は、その大きな音にも気づかないようで、目を閉じて眠っていた。 その顔は透けるように、雪のように真っ白で、苦しみも悲しみも感じさせないぐらいに穏やかだった。 「間に合いました…よね?」 そう尋ねる私に母親は首を振った。 今朝来た時には、小さな音を立てて動いていた機械も、その役目が終わった事を主張しているかのように沈黙している。間に合わなかったと音を出さずに示している。 「そんな…」 雪が見たい―ささやかな夢、無垢な願い。 “後少しで、叶ったのに” 外に置いた機械のボタンを押すと、噴き出す雪が強い風にさらわれ、涙色の空を白く染め上げていった。 私に出来るのは、少女がこうして白く飾られた道を歩いて逝くのを願う事ぐらい。 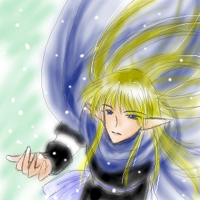
おやすみなさい。 どうか安らかに― 外からは、子供たちが遊びはしゃぐ声が聞こえてくる。 なのに、彼は窓の外―舞い落ちる雪を、眉間にしわを作って見つめていた。 “まるで、兄さんみたい” 思った彼女は、声をかけた。 「どうしたの?」 「いえ…」と、考えを追い出すかのように首を振った彼は、彼女をまっすぐに見て、その名を呼ぶ。 「ん?」 伸ばした両手で、彼女の身体を捉えると、ほぅ…と溜息一つを肩口に落とし、彼は言った。 「ずっとそばに居てくださいね」 重なる面影。あの少女みたいに消えてしまわないよう― 最初、エアトルさんと間違えた方残念。ちょっと引っ掛けもどきで書いてみました(ぇ 日記では差をつけるために、ですます調で書いてますが、それは一部の相手にだけだったり。 上司として立つ場合や古くからの友人には、ですます言葉使いませんよ。その辺きっちり線引きしてます。 そんな器用なのか不器用なのか分からない彼ですが、今も昔も、失う事には極端に臆病です(謎 挿絵はクエストを終えた当日に、日記にはまともに書けない鬱憤を晴らすかのごとく、描いてしまったものの縮小図。 投稿ボタンを押した直後、髪をくくってない事に気づきました。PHI限定だから、ついうっかり忘れてしまう…(。。; |

![]()